
江口寿史展
EGUCHI in ASIA
2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館
| 2022/12/03 |
|
前回、20世紀初頭に前衛美術が勃興した時期と「スペイン風邪」の世界的大流行との関係について、これまで触れられてこなかった美術史的な次元での「忘却」について触れた。これについては、戦争のように加害/被害にまつわる人為性が明確でない感染症では、人の営みの集積である歴史への翻案が困難であった可能性もある。だが、今回のパンデミックで過去に起きたそんなにも大きな忘却が明白になったいま、今後この時期の美術史はいったいどのように書かれるのだろうか。
そもそも歴史には、最低でも100年を単位とするような遠望性がある。言い換えれば、いまから100年が経過した未来の時点から現在を振り返ったとき、21世紀初頭、2020年代のアートに与えたコロナ・パンデミックの影響が、歴史からすっかり抹消されていたとしたらどうだろう。歴史の記述にそんな極端な瑕疵(かし)が起きるはずがない、と即座に思うかもしれない。だが、100年前の美術史の記述において実際にそれは起こったのだ。
いったいどのようにしたら、このような忘却を食い止めることができるだろう。それは同時に、わたしたちが現状なお続く際限のない感染の波の繰り返しから脱出する鍵にもなるかもしれない。もっとも、これは新型コロナ感染症が――いままさにそうなりつつあるように――インフルエンザやそれこそ「風邪」と同じ扱いを受けるようになることで、かつての日常が取り戻されるというのとはまったく別の次元の話だ。というよりも、そうなることでわたしたちは進んで過去の感染症の大流行を忘却し、歴史と引き換えに目の前の「日常」を回復してきたのではなかったか。
やはり、なにか根本的な認識の転換が必要なのだ。それは「ウイズ・コロナ」や「ポスト・コロナ」といった標語で片付くような代物では到底ありえない。
仮に現在のコロナ・パンデミックがひとつの山を超えたとしても、そのあとも別の新型ウイルスによるパンデミックが人類と対峙(たいじ)するだろう。わたしたちが自覚しなければならないのは、それがいったいどのような性質のウイルスなのか、という問題以前に、わたしたち人類の一人ひとりがそうした多種多様なウイルスの運び手になっている、という認識の転換なのではないか。
運び手といってもそれは、なにかものを運ぶ、というのとはむろん違っている。私たち一人ひとりの呼気であり発汗であり、会話でありといった人と人との交わりそのものに感染症拡大の要因があるのだ。言い換えれば、わたしたちが生きて活動している、という生命現象そのものがウイルスの活動を活性化していることになる。
そのような活性化の一切を絶とうとするなら、わたしたちは生きることそのものを途絶させなければならなくなる。言うまでもなくそんなことはありえない。としたら、考えを逆転するしかない。つまり、わたしたち人類そのものが、根本的に交雑的な性質をもつものなのだ。と同時に、様々な局面で浮上する純化や無菌といった抽象化による無意味な理想化と抵抗し続けるしかない。
20世紀のアートを通じてモダニズムが推し進めた造形の純化や余計な装飾などの徹底的な排除は、根本的に交雑する存在であることに気づいてしまったわたしたちからすると、浄化という名のもと、歴史への免疫低下をもたらしていたように思えてならない。(椹木野衣)
=(12月2日付西日本新聞朝刊に掲載)=
椹木野衣(さわらぎ・のい)
美術評論家、多摩美術大教授。1962年埼玉県生まれ。同志社大卒。著書に「日本・現代・美術」「反アート入門」「後美術論」「震美術論」など。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)
九州国立博物館
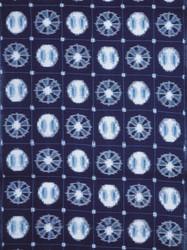
2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)
九州芸文館