
江口寿史展
EGUCHI in ASIA
2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館
| 2022/09/16 |
|
東京でも夏の終わりを感じさせる秋の風が吹くようになったが、コロナ禍の第7波はこれまでの定型的な周期と違い、増えたり減ったりを繰り返し、以前のような収まりを簡単には見せそうにない。人の移動や行動を制限せず、マスクの着用も緩和しての初めての夏だったことや、帰省や夏休みの旅行、各所で開かれた催しごとも(感染対策を施して行ったとはいえ)その一因かもしれない。
けれども、波が見えなくなるということは、言い換えれば新型コロナがいよいよ日常に定着しつつあるということでもある。ひょっとすると、このような状態が、かつて言われた「ウィズコロナ」なのだろうか。もちろん医療現場が逼迫(ひっぱく)したままというわけにはいかないが、もしも現在のような暮らしのスタイルが「ウィズコロナ」であり、もっと言えば「ポストコロナ」なのであるなら、コロナ以前のかつての「日常」は、もう二度と戻ってこないのかもしれない。
かつてとまったく同様ではないにせよ、アートに引き寄せて言えばこの夏、「コロナ以前」にも増して多くの芸術祭に足を運ぶ機会があった。個人的にも「越後妻有 大地の芸術祭」、「瀬戸内国際芸術祭」、「リボーン・アートフェスティバル」(石巻)、「葦の芸術原野祭」(斜里)などに向かったが、規模にこそ大小はあるものの、延期や中止に追い込まれることはなく、各所の状況に即して淡々と開催されていた。むろん、芸術祭が展覧会である以前に観光事業としての側面を色濃く持つ以上、その「成果」は具体的な「数字」となって跳ね返ってくるものの、そもそも祭りとは数字でその成否を測れるものであったのかどうか。
前から不思議に思っていたことがある。というのは、各地に昔から伝わる祭りや儀礼は、少なからず疫病退散を祈願して行われてきた。にもかかわらず、いざ疫病が流行ってみると、そのことごとくが中止に追い込まれた。これはいったいどういうことなのだろう。疫病が恒常的に猛威を振るう日常があるからこそ、そのような祭りは起こったのではなかったか。裏返せば、人が集い密に接することから感染の恐れがあったとしても、祭りは絶えることなく伝わり、催され続けてきた。

これは、祭りが本来のあり方を失い、娯楽や事業としての性格をあまりに強めてしまったことを意味する。おそらくかつての祭りは、日常よりもはるかに濃密な交感によって、多少の感染拡大があったとしても、それでもなお行われなければならなかった。衛生環境や治療の対処など現在とは比べ物にならなくてもそうだったのだ。祭りとはおそらく、ある程度の感染機会であることを承知のうえで行われてきたことになる。別の角度から見れば、それくらいの切迫感が日常そのもののなかにあったことになる。
そういう意味では、コロナ禍でなお開催される祭りや芸術祭は、制限された不完全なかたちでの祭りというよりも、古来あった本来の祭りのかたちに、逆に戻りつつあると言えるかもしれない。
多少の感染者は出ても祭りは開かれていい、ということが言いたいわけでは決してない。娯楽や観光に偏りすぎていた祭りの性質をもう一度見直し、「元に戻す」ばかりを優先しないことが、実は「アフターコロナ」ではなく、「コロナ以前」のさらに「以前としての常態」を想い起こさせることになるのではないか。美術やアートにとってもそれはなんら違いがない。(椹木野衣)
=(9月6日付西日本新聞朝刊に掲載)=
椹木野衣(さわらぎ・のい)
美術評論家、多摩美術大教授。1962年埼玉県生まれ。同志社大卒。著書に「日本・現代・美術」「反アート入門」「後美術論」「震美術論」など。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)
九州国立博物館
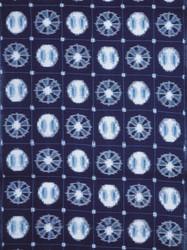
2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)
九州芸文館