
江口寿史展
EGUCHI in ASIA
2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館
| 2022/06/17 |
|
国際芸術祭のシーズンがやってきた。とりわけ今年は昨年から延期となった国内での「芸術祭」の嚆矢(こうし)、「越後妻有 大地の芸術祭2022」や国内最大の芸術祭「瀬戸内国際芸術祭 2022」がすでに開幕している。また大型芸術祭では「あいちトリエンナーレ」から改名し新たな出発となる「あいち2022」のほか、後期を今年に配した「Reborn-Art Festival 2021-2022」(宮城)、さらには「岡山芸術交流2022」など目白押しだ。また海外でも2年に一度の「第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭」、ドイツ、カッセルで5年に一度開催される「ドクメンタ」展の「ドクメンタ15」と、世界でも最大級の催しが集中している。
このうち私は国内での二大芸術祭と呼べる「大地の芸術祭」と「瀬戸内国際芸術祭」に開幕から足を運んだ。「Reborn」は昨年の前期から見ている。海外は渡航が緩和されたものの長期を要するので具体的な計画は立てられていないが、ほかにも国内での芸術祭には各所へと足を運ぶ予定だ。まだ結論めいたことを言う段階ではないが、コロナ禍での大型国際芸術祭、現代美術展に共通の傾向がすでに見え始めているように感じている。
ひとつは、会期の長期化だ。これはコロナのいわゆる「波」が会期に掛かり移動などに制限が生じたとしても、そうでない時期にある程度の挽回が図れるように考慮した結果であると思う。芸術祭はその名の通り「祭り」なので、その象徴が収穫祭であるように、日本では四季の折々と深く連動する。ところがコロナ禍では「春夏秋冬=四季」に代わって「感染の波」が年間の人々の行動を左右する――これは本連載でも繰り返し強調してきた。これにより芸術祭でも季節に応じて魅力を発揮する祝祭的要素が薄くなりつつある。さらに長期化は、貯めに貯めた力を一気に解放するという「祝祭」とは逆の感触を受け手に与えるかもしれない。こうした一連の変化の結果、国内での芸術祭は総じて従来の「芸術祭」の典型からは緩やかに離脱を図りつつあるように思われる。
もっとも、芸術祭がコロナ・パンデミックの前から抱えていた課題のひとつがその継続性、つまり芸術祭のない期間にいかに次回へと至る機運を持続するかにあったことから考えると、芸術祭そのものがその名称も含めて大きな岐路に立っているのかもしれない。もちろん、芸術祭が作品の「鑑賞」というよりもインバウンドの語に代表される「観光」をモデルに組み立てられていたことからのリスク軽減は、海外からの訪日まで視野に入れるといまだ回復のめどが立たない以上、どうしても考えざるをえない。
さらに言えば、パンデミックがそのような「世界観光」の加速化によりあっというまに地球の隅々まで広がったことを考えれば、こうした人の移動を可能にするグローバリズムそのもののが仮に回復しても、それはそれで次なるパンデミックがいつどこで起きても不思議ではない大きなリスクと共存していくことになる。その余波を受けるのはなにも芸術祭だけではない。美術館での展覧会でも同様だろう。やはり根本からアートの基底が変化しつつあるのだ。
こうしたなかで芸術祭は少しずつ芸術運動のようなものになりつつある。だが、観光としての祭りを牽引するのが経済だとしても、「運動」ではそうはいかない。では、そもそもが何のためのアートだったのか、それこそがコロナ禍で試されつつある。(椹木野衣)
=(6月9日付西日本新聞朝刊に掲載)=
椹木野衣(さわらぎ・のい)
美術評論家、多摩美術大教授。1962年埼玉県生まれ。同志社大卒。著書に「日本・現代・美術」「反アート入門」「後美術論」「震美術論」など。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)
九州国立博物館
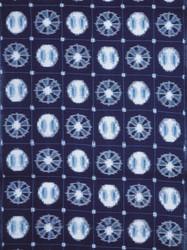
2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)
九州芸文館