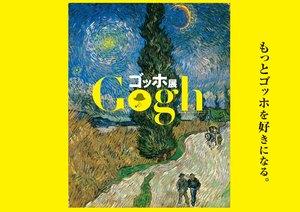
ゴッホ展
響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
2021/12/23(木) 〜 2022/02/13(日)
09:30 〜 17:30
福岡市美術館
| 2021/12/28 |
|
■ゴッホ 8つの謎を探る旅─エピローグ
(この記事は2011年2月5日付で、内容は当時のものです)
一つの問いが気にかかっていた。昨年9月、南仏アルルでファン・ゴッホ(1853~90)の足跡をたどるために乗ったタクシーの運転手セバスチャン・トレサン氏が何げなく発した問いだ。夏の観光シーズンはアルルを訪ねてくる外国人を乗せることが多い―そんな話がきっかけだった。
「いつも感じるのだが、ヨーロッパ各国からの人々は古代劇場や共同浴場跡など古代ローマの遺跡に連れて行けという。だが、日本をはじめ韓国、香港などアジアからの観光客は、跳ね橋やヒマワリ畑、アリスカンの並木道などゴッホ縁(ゆかり)の場所に、と言う。アジアの人たちは、なぜゴッホの足跡を追いかけるのか?」
意表を突く質問だった。答えに詰まった。「根底に何か共通するアジア的心性があるのだろうか? それとも、全くほかの理由だろうか。韓国語や中国語に訳されているガイドブック『地球の歩き方』のためだろうか」。堂々巡りの思考の中で、思い出したのはかつて書評で紹介されていた本のことだった。
その本とは、一昨年末、フランスで刊行された尾本圭子著『ヴァン・ゴッホ オーベールへの日本人の巡礼 ポール・ガシェ家の芳名録の研究と紹介』である。晩年のゴッホの主治医で、彼の絵のコレクターでもあった仏・オーベール・シュル・オワーズの医師ガシェの家に保管されていた20点ほどのゴッホの絵を見るため、1920年代初期から30年代末まで、ガシェ家を訪問した日本人芸術家たちが署名した芳名録(ギメ美術館蔵)を復刻したものだった。
そこに記された錚々(そうそう)たる名前に圧倒された。洋画家の佐伯祐三や里見勝蔵、日本画家の土田麦僊(ばくせん)や小野竹喬(ちっきょう)、歌人の斎藤茂吉と、その数250人。福岡県出身の画家・坂本繁二郎も23年に訪れていた。
これらの人々は、ゴッホの何に引かれ、はるか異国に彼の作品を見に行ったのか? それを問うことが、アルルの運転手への回答につながるのではないか?
その前に日本でのゴッホの受容史に触れておきたい。わが国へのゴッホの紹介は1910(明治43)年、森鷗外(おうがい)が雑誌「スバル」で彼の名を挙げたのが嚆矢(こうし)とされる。間もなく、武者小路実篤(さねあつ)ら雑誌「白樺」のメンバーを中心にゴッホの画業と生涯が熱く語られることになる。そこではゴッホは、生きるのにさまざまな障害を伴う近代をピュアに全身全霊で生き抜いた画家として紹介され、当時の青年たちもゴッホの姿に、人生いかに生きるか、芸術と人生はどうあるべきか―など人生の指針を重ね合わせた。
その後もゴッホは詩や演劇でたたえられる一方、彼の病気を病理学的に解明しようとする論文、ゴッホの足跡を追う紀行・写真集などが続々と刊行される。その多くは、ゴッホの貧窮を清貧に、短命を夭折(ようせつ)に、自殺を自決に、狂気を風狂へと美化し、不遇な人生を送ったこの画家に限りない共感を寄せた。そこには、どこか判官びいき的な日本人の心性も交錯した。ゴッホとは、ある意味では西洋を意識し、西洋との対峙(たいじ)の中で、進路を探っていった日本近代や日本近代美術の一つの道標ではなかったのか。

昨年末から、日本、オランダ、フランスを舞台に、ゴッホをめぐる8つの謎を探る旅を紙面で続けてきた。ゴッホの絵の画面はなぜあれほど輝いているのか、彼の愛した女性は誰だったのか―など、8つの謎を追いかけた。全てが難問、探ることで、かえって謎が深まったものもあった。
ただ、この旅で感得したのは、ゴッホが絵画に向き合ったひたむきさ、その絵画表現への強烈な情熱だった。彼は従来にない新しい絵画を描こうと、身を削り、一切の妥協を排し、極限まで自分を追い詰め戦った。死ぬ1カ月前の手紙にも、こう記している。
〈僕は、自分の仕事のことを考えるとひどく辛(つら)い思いになる。(中略)僕は、僕が描き出したいと願ったことの、ほんの少ししか実現できていない。いつかはきっと僕も、もっといい絵が作れるだろう。でもまだそこへは至っていない〉
さて、美術評論家の高階秀爾氏は「ゴッホは目に見えるものしか描かなかった」と書いている。その伝に従えば、ゴッホは、新しい“ノンフィクション”ともいえる絵画を目指した画家ではなかったのか。想像や虚構ではなく、あくまで見えるものから出発し、それを過去には存在しなかった新しい文体(技法)や話法(様式)、時には幻想も化合させつつ絵画化しようとした画家ではなかったか。
ようやく、アルルの運転手への回答が見えてきた気がする。それは原郷探しの旅なのだと。ヨーロッパの人々にとって、古代ギリシャやローマの遺跡こそ彼らの精神文化の古里、原郷であろう。一方、近代を西欧から輸入したアジアの人々、なかんずく日本人にとって、自分たちの精神文化の一つの起源、出自は「西欧近代」ではなかったのか。その出自、原郷に強固に結合した人物こそゴッホであり、彼の足跡をたどることは、アジアの人々にとって自らの精神文化の原郷に立ち返る旅ではないのだろうか?
もう一人、この連載の1回目で紹介した、アルルからゴッホの花・ヒマワリを摘んで、100年目の命日にパリ近郊のゴッホの墓に供えた「Hiroaki KAMIZONO」氏のことも気になっていた。彼の写真、それは多くを語りかける1枚だったからだ。
カミゾノ氏のことはネット検索であっけないほど簡単に分かった。神園宏彰氏。50歳。福岡市在住だった。
神園氏には、ゴッホ展開催中の九州国立博物館で会った。熱烈なゴッホファン。美大に学び、定期的に絵と写真を発表していると言った。
88年、図書館で手にした画集で、その年がゴッホがアルルで『ひまわり』を描いて100年になるのを知った。少年時代、美術の教科書で見て感動した『アルルの跳ね橋』の記憶が一気に甦(よみがえ)った。自分を呼んでいる気がした。カメラを担いでゴッホ縁(ゆかり)の地をまわった。撮った写真は「アサヒグラフ」に掲載され、福岡市美術館で写真展も開催された。
2年後の90年、30歳の時。ゴッホの没後100年の年に、再びゴッホ縁の地に撮影に赴いた。命日の前日、ゴッホと弟のテオのためにアルルで2本のヒマワリを摘んだ。ぬらしたタオルで茎の切り口を包み、列車に乗った。翌日、パリ郊外の墓に赴き、2人の墓に1輪ずつ供えた。その帰り道、ゴッホが下宿していた家の近くに張ってあったのがあのポスターだった。
「ポスターを見たとき、没後100年のゴッホが、僕を待っていてくれたと思った。だから夢中でシャッターを切った。あれから20年、今度は没後120年の彼が、九州の僕に会いにきてくれた。そんな気がするんです」(藤田 中)=おわり
取材協力(当時) オランダ政府観光局、フランス観光開発機構、西鉄旅行
▼「ゴッホ展―― 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
2021年12月23日~2022年2月13日、福岡市中央区の市美術館。オランダのクレラー=ミュラー美術館、ファン・ゴッホ美術館の収蔵品から、ゴッホの油彩画、素描など計52点のほか、ミレー、ルノワールなどの作品も紹介する。主催は福岡市美術館、西日本新聞社、RKB毎日放送。特別協賛はサイバーエージェント。協賛は大和ハウス工業、西部ガス、YKK AP、NISSHA。観覧料は一般2000円、高大生1300円、小中生800円。1月3日、10日を除く月曜休館。12月30日~1月1日と4日、11日も休館。問い合わせは西日本新聞イベントサービス=092(711)5491(平日午前9時半~午後5時半)。
■「ゴッホ展ーー響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケットのご購入は
コチラから。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)
九州国立博物館
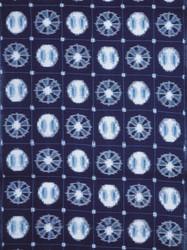
2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)
九州芸文館