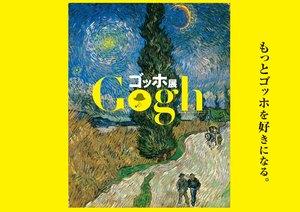
ゴッホ展
響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
2021/12/23(木) 〜 2022/02/13(日)
09:30 〜 17:30
福岡市美術館
| 2021/12/27 |
|
■ゴッホ 8つの謎を探る旅─第6の謎
(この記事は2011年1月15日付で、内容は当時のものです)
圧倒的な光量で街を照らしていた昼から一転、紫紺の闇が支配していた。鏡のように滑らかな川面に街灯が瞬く。昨年10月20日、南仏アルルを流れるローヌ川を眺めていた。眼前にフィンセント・ファン・ゴッホ(1853~90)の『星降る夜』の景色が広がっていた。10分も歩けば『夜のカフェテラス』の店もある。今、自分がゴッホが描いた風景の中にいる。そんな高揚感が込み上げてきた。
ゴッホはアルルの夜に豊かな色彩を与えた。夜だけではない。『ひまわり』や『アルルの跳ね橋』…。明るい色のあふれる代表作をこの地で描いた。パリからアルルに移ったのは1888年3月。翌年の5月に自らサンレミの療養院に移るまでに残した油彩は約200点。画家としての「開花期」だった。
評伝の多くは、ゴッホはこのアルル時代、南仏の明るい太陽と豊かな色彩、そして理想郷としての「日本」のイメージを追い求めたと書いている。だが南仏の数ある町の中から、アルルを選んだ理由にはほとんど触れぬままだ。謎はもう一つ。ゴッホはアルルに画家の共同体を作ろうとした。なぜなのか?

謎を探るため、パリ時代まで時計の針を戻してみよう。パリで彼が出会ったのは、当時、前衛とされた印象派の画家や、さらに新しい様式をつくり上げたスーラやゴーギャンたちだった。ゴッホは、2年間のパリ生活で、独自のテーマと様式の必要性を痛感していた。近代都市のパリは、すでに主題としての目新しさは乏しくなっていた。セザンヌやモネは南仏の海岸を描き、ゴーギャンやベルナールは仏東部のブルゴーニュ地方を開拓していた。ゴッホも「パリ以外」に自分の活路を求める必要があった。
一方で、オランダの農村出身のゴッホは、都会のパリになじめず、人間関係にも酒浸りの生活にも疲れ始めていた。弟テオへの手紙では逃避行の場所として、南仏を持ち出している。
〈南仏のどこかに引っ込んで、人間としてもたまらないたくさんの連中に会わないようにしたい〉
アルル行きの理由について、ゴッホは多くを語っていない。それだけに想像の余地は大きい。
親友の画家ロートレックが、こうささやいたという説がある。「黒い眉、長いまつげ、卵形の典雅な面立ち、気品のある物腰。ギリシャの末裔(まつえい)であるアルルの女は素晴らしい」
1887年、パリで開かれた南仏の祭典「太陽の祭典」に影響を受けたとする説もある。また、南仏マルセイユ出身の画家で、厚塗りで宝石のように輝く絵を描いたモンティセリに憧れ、南に向かったという説もある。
決定打がない中、アルルの石畳を歩いた。案内してくれたガイドのマリーロール・パリコさんのひと言にはっとした。「ゴッホが気に入ったのは、アルルが持つ田舎的な部分と都会的な部分のバランスだったのでは?」
当時のアルルは、田園風景が広がる一方で、鉄道が走り、近代的な工業も発達し始めていた。ゴッホが描きたかった、自然の中での人間の営み、工業も含めた新しい人間の営みがそこにはあった。彼が求めていた複数の条件の交点が、アルルだったのではないか。
青い空に、刷毛(はけ)ではいたような秋の雲が浮かんでいた。ゴッホが画家たちの共同生活の拠点にしようとした「黄色い家」の跡は、アルル駅のすぐ近くにあった。ゴッホはここに、新しい芸術を目指す画家仲間を呼び、刺激し合いながら制作する共同体の実現を夢見ていた。ゴッホは、そのアイデアをどこから得たのか?
ヒントは書簡集の中にあった。ゴッホは画家の共同体に修道院のイメージを仮託していた節もあり、画商である弟のテオ宛ての手紙に、テオが共同体に参加すれば〈(君は)最初の画商使徒になるだろう〉と書いた。また、〈芸術家たちは協同して絵を組合に渡し、少なくとも組合が会員の生活を保障し、制作が続けられるような仕方で売上金を配分する、これよりいいやり方は見つからないだろう〉とも記している。
この時代、画家は総じて食えなかった。だから芸術家の共同体を理想に掲げること自体は、ドイツのナザレ派や英国のラファエル前派などの画家グループにも共通している。ゴッホの独自性は、その共同体にジャポニスムや「日本」のイメージを絡めた点だ。
さて、それでは19世紀の西洋人の目に日本はどう映り、どう伝えられていたのだろうか。江戸末期から明治初期に来日した西洋人の観察記録を基に、日本の前近代を浮き彫りにした評論家・渡辺京二氏の『逝きし世の面影』を手に取った。悠長、簡素、陽気、礼儀、親切―。記録者たちは、西洋が失ってしまった、親和性に満ちた前近代の文明への郷愁を、日本や日本人に見いだしていた。
同時代を生きたゴッホも同じだったのではないか。ピエール・ロチの小説『お菊さん』、雑誌「芸術の日本」などの書物から、日本への幻想を膨らませていたようだ。
〈日本美術を研究すると、明らかに賢く哲学的で、知的な人物に出会う。(中略)まるで自分自身が花であるかのように自然の中で生きる〉
ゴッホが手紙に記している「日本人」は、知的で自然に没入して生きる素朴な人物として像を結ぶ。
美術史学者の木下長宏氏は「ゴッホ自身の理想を日本、日本人に重ねているに他ならない」と指摘する。ゴッホは、自らのイメージに合致する情報のみを拾い上げ、独自の日本人の自然観、精神世界をつくり上げ、傾倒していたというのだ。
ゴッホがいう「日本」とは、衆目を集めるうたい文句でもあった。アルル到着以降、弟のほか、ゴーギャンやベルナールなど画家仲間に宛てた手紙には「まるで日本にいるようだ」「日本のように美しく」と繰り返し書きつづった。「自分がいるアルルこそがユートピアとしての日本そのものであり、芸術家にとっての理想の地だ」とアピールし、一刻も早くこの地を訪れるべきだと誘った。
木下氏は言う。「ゴッホはパリでは得られない新しい刺激がある南仏、今後、注目を集めそうなスポットとしての南仏、そこに『日本』というキーワードを組み合わせることで、自ら、そして自らの絵画の活路を見いだそうとした」
そこには「炎の画家」や「狂気の画家」のイメージはない。美術界全体の状況を俯瞰(ふかん)し冷静に進む道を探った「戦略家」の姿が浮かぶ。(佐々木直樹)
取材協力(当時) オランダ政府観光局、フランス観光開発機構、西鉄旅行
▼「ゴッホ展―― 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
2021年12月23日~2022年2月13日、福岡市中央区の市美術館。オランダのクレラー=ミュラー美術館、ファン・ゴッホ美術館の収蔵品から、ゴッホの油彩画、素描など計52点のほか、ミレー、ルノワールなどの作品も紹介する。主催は福岡市美術館、西日本新聞社、RKB毎日放送。特別協賛はサイバーエージェント。協賛は大和ハウス工業、西部ガス、YKK AP、NISSHA。観覧料は一般2000円、高大生1300円、小中生800円。1月3日、10日を除く月曜休館。12月30日~1月1日と4日、11日も休館。問い合わせは西日本新聞イベントサービス=092(711)5491(平日午前9時半~午後5時半)。
■「ゴッホ展ーー響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケットのご購入は
コチラから。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)
福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)
九州国立博物館
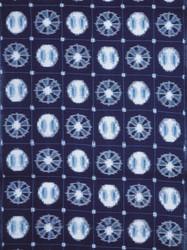
2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)
大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)
九州芸文館